ニキビができる原因
ニキビ発生の原因と最近の知見
ニキビは誰もが一度は悩んだことのある身近な肌トラブルです。
なぜニキビができるのでしょうか?
ニキビは一つの原因ではなく、毛穴の詰まりやアクネ菌の増殖など、いくつかの要因が重なってできるものです。
このページでは、ニキビができる仕組みをわかりやすく解説し、その原因の全体像をつかめるようにまとめました。
それでは、一緒にニキビの原因を見ていきましょう。
この記事の目次
ニキビはなぜできるの?(総論)
ニキビ(尋常性ざ瘡〈ざそう〉)は、思春期の時期に約8~9割の方が経験するごく身近な皮膚のトラブルです。
毛穴に皮脂が詰まり、そこに アクネ菌(皮膚にいる常在菌の一種)が増殖して炎症を起こすことで、赤いブツブツ(丘疹や膿疱)や白い膿をもった吹き出物が生じます。放っておくと炎症が強まり、周囲の皮膚まで傷つけて ニキビ跡(瘢痕) が残ることもあります。
ニキビは「青春のシンボル」などと言われることもありますが、医学的には 毛包(もうほう)=毛穴の病気 であり、適切なケアと治療が必要な皮膚疾患です。
まずは正しい原因とメカニズムを理解していきましょう。
ニキビはなぜできるの?(原因とメカニズム)
ニキビのでき方にはいくつかの要因が重なっています。特に重要なポイントは次の4つです。
- 皮脂の過剰分泌
- 毛穴のつまり
- アクネ菌の増殖
- 炎症(赤ニキビ化)
皮脂の過剰分泌
思春期になるとホルモン(主に男性ホルモン)の影響で皮脂腺が刺激され、大量の皮脂(皮膚のあぶら)が分泌されます。皮脂は本来お肌を守る役割がありますが、多すぎると行き場を失い毛穴の中にたまってしまいます。
毛穴のつまり
お肌の生まれ変わり(ターンオーバー)の乱れなどにより毛穴の出口付近の角質が厚く硬くなると、毛穴が狭く塞がって皮脂が外に出にくくなります(異常角化)。こうして皮脂が詰まった毛穴には白い角栓(コメド)ができます。
この 詰まった毛穴(面皰[めんぽう]) がニキビの第一段階です。思春期のお子さんは成長に伴う皮膚代謝の変化で毛穴がつまりやすくなります。
この「異常角化と毛穴の詰まり」については別ページで詳しく解説しています。
アクネ菌の増殖
毛穴に皮脂が詰まると、その中は皮脂たっぷり&酸素少なめの状態になります。この環境は皮膚の常在菌である アクネ菌(学名: Cutibacterium acnes)が大好きな条件です。
アクネ菌そのものは誰の肌にもいますが、毛穴の中で異常に数が増えすぎると問題です。菌が増殖する過程で種々の 炎症物質 が放出され、毛穴の壁や周囲の組織を刺激します。
炎症(赤ニキビ化)
アクネ菌の刺激などにより免疫反応が起こり、毛穴周囲に炎症(赤みや腫れ)が生じます。その結果、赤い丘疹(いわゆる赤ニキビ)や膿をもった膿疱(黄ニキビ)へと進行します。
炎症が強いと毛穴周囲の皮膚まで破壊され、治った後にクレーター状やケロイド状のニキビ跡が残ることもあります。
以上がニキビ発生の主な仕組みです。この4要素はほとんどのニキビに共通する基本原因であり、逆に言えばニキビ対策・治療も「皮脂を抑える」「毛穴づまりを取る」「菌の増殖を抑える」「炎症をしずめる」の4方向からアプローチします。
なお、ニキビができやすいかどうかには体質(遺伝的な要素)も影響します。家族(特に両親)がひどいニキビに悩んだことがある場合、お子さんもニキビができやすい傾向があります。
また毛穴や皮脂腺の大きさ・数といった肌質の個人差も関与します。
思春期と大人ニキビの違い
思春期ニキビと大人ニキビ(アダルトニキビ)では、ニキビができる主な原因や肌の状態に違いがあります。それぞれの特徴を見てみましょう。
思春期にニキビができやすい理由
皮脂の分泌量はホルモンによってコントロールされています。特に男性ホルモン(テストステロンなど)は皮脂腺を大きく発達させ、皮脂の産生を促す作用があります。
思春期はホルモン分泌が活発に
男女とも思春期には副腎や性腺の発達によりホルモン分泌が活発になるため、皮脂も急増し毛穴の出口が追いつかず詰まりやすくなります。さらに成長期には毛穴周囲の角質細胞も増殖しやすくなるため、「皮脂が増える」+「毛穴がつまりやすい」状態が重なってニキビができやすくなるのです。
実際、ニキビは思春期~20歳前後で発症のピークを迎え、約85%もの10代が経験するとされます。おでこや鼻・あごなど脂っぽい部位に多発するのも、皮脂腺がその部位に集中しているためです。
ホルモンバランスの変動
もう一つ見逃せないのが女性ホルモンと肌状態の関係です。女性の場合、思春期以降は月経周期に伴ってホルモンバランスが周期的に変動します。
生理前には黄体ホルモン(プロゲステロン)が増えて皮脂の分泌を促すうえ、ストレス耐性を下げる作用もあるため、生理前にニキビが悪化しやすいと言われます。
同じ理由で、思春期のお子さんでも寝不足だったりテスト期間でストレスが多かったりするとニキビが増えがちです(後述)。
一方、生理が始まると今度は皮脂分泌を抑えるエストロゲンが優位になるため、肌の調子が落ち着く傾向があります。
このようにホルモン環境の揺らぎもニキビに影響するポイントです。
大人のニキビ(思春期以降のニキビ)
「ニキビ=十代特有のもの」というイメージがありますが、20代以降もニキビができることは珍しくありません。特に女性の場合は、25歳を過ぎてもニキビに悩む人が多く、30~40代でも約5%前後の女性にニキビがみられるとの調査もあります。
思春期のニキビと比べると、大人のニキビ(いわゆる「大人ニキビ」)はあご周りや口周りなど下顔面にできる傾向があります。原因としては思春期と共通する部分も多いですが、次のような特徴的な要因が考えられます。
ホルモンバランスの乱れ
大人の女性では、月経前後や妊娠・出産、更年期などホルモン環境の変化によって皮脂分泌が増えたり肌の防御機能が低下したりしてニキビが悪化することがあります。特に生理前後のニキビ悪化はよくみられます。
また婦人科系の病気(例:多嚢胞性卵巣症候群<PCOS>など)による男性ホルモン過剰(高アンドロゲン血症)が潜在しているケースもあります。
肌の新陳代謝の低下
加齢に伴いターンオーバーが遅くなるため、古い角質が毛穴に残りやすくなります。乾燥や紫外線ダメージで毛穴の周りの皮膚が硬く厚くなっていることも多く、結果として毛穴詰まりが起こりやすい肌質になっています。
生活ストレス
就職・結婚・妊娠・育児など環境の変化が多いのも大人世代の特徴です。忙しさや対人関係のストレスから自律神経やホルモンのバランスが乱れ、皮脂分泌や免疫の働きに影響してニキビが長引く要因となりえます。
睡眠不足や喫煙・偏った食生活など不規則な生活習慣も重なりがちです。
不適切なスキンケア
大人世代では「ニキビもあるのに乾燥もする」という混合肌の方が増えます。肌の乾燥を防ごうと油分の多い化粧品を使いすぎると毛穴をふさぎ悪化の原因に。
また、「清潔にしなきゃ」と1日に何度もゴシゴシ洗顔したり、刺激の強い洗顔料・ピーリング剤を頻用すると、皮脂を落としすぎて肌が乾燥・敏感になり逆効果です。
間違った自己流ケアがニキビをこじらせるケースは大人にも見られます。
大人ニキビはこうした要因が絡み合い、慢性的にポツポツとした吹き出物が続くのが特徴です。
思春期に比べて皮脂量は多くないため赤く炎症の強いニキビは少なめですが、その代わり治りにくく、治ってもまた同じ所に繰り返しできる…といった状態になりがちです。
「思春期はニキビ知らずだったのに、大人になってから繰り返す」と悩む方も珍しくありません。根気よく生活習慣を整え、必要に応じて皮膚科での治療を検討しましょう。
生活習慣・環境によるその他の悪化要因
ニキビは上記のような体質的・内分泌的な要因に加え、日々の生活環境も深く関係します。「睡眠不足でニキビが増える」「食べ過ぎるとニキビができる」などと昔から言われますが、これはあながち迷信ではありません。
最近の研究でも、食事内容やストレス等がニキビの発生・悪化に影響しうることがわかってきました。以下のポイントに留意してみましょう。
まず押さえるポイント
- 日常の”積み重ね”が、毛穴の詰まりと炎症を左右します。
- 下の小見出しから、心当たりだけ拾い読みでOK。
- 2〜4週間、1つずつ試し変化が出たら継続。悪化する場合は受診を。
食事(高GI/乳製品)
脂っこい食べ物よりも、糖分の多い食品や飲み物がニキビに影響する可能性が指摘されています。
いわゆる洋菓子・清涼飲料など血糖値を急上昇させる食品を頻繁に摂ると、インスリンやIGF-1といったホルモンの分泌が増え、皮脂腺を刺激してニキビを悪化させると考えられます。
実際、高GI食品※を控えて低GI食に切り替えるとニキビが有意に減少したとの報告もあります。(※GI=グリセミック指数。高GI食品の例:砂糖菓子、ジュース、白パンやスナック菓子など)
また 牛乳・乳製品の過剰摂取も一部で関連が疑われています。
とはいえ食事だけが直接の原因ではありません。栄養バランスの良い食事を心がけつつ、甘い物は適度に楽しむ程度が良いでしょう。
睡眠不足・生活リズムの乱れ
夜ふかしや昼夜逆転の生活は ホルモン分泌のリズムを乱し、皮脂分泌の調整機能も狂わせてしまいます。特に成長期のお子さんは体内時計の影響が大きく、慢性的な睡眠不足は肌の新陳代謝の妨げにもなります。
反対に十分な睡眠と規則正しい生活リズムはお肌のコンディションを整える基本です。「寝る子は育つ、肌も育つ」です。毎日できるだけ決まった時間に就寝・起床し、夜更かしは控えましょう。
ストレス・心の状態
部活や勉強、人間関係などのストレスも ホルモンバランスや免疫力に影響し、ニキビを悪化させる一因となります。
実際、試験期間中はニキビが悪化したり、反対に長期休暇でリラックスするとニキビが改善したりするケースもあります。またストレスによる睡眠不足・食生活の乱れが間接的に影響する部分も大きいでしょう。
適度に気分転換・リラックスする時間を持つこともお肌には大切です。
ヘアケア・化粧品(ノンコメドジェニック/落とし残し)
おでこに前髪がかかっているとその部分にニキビができる、なんて話を聞いたことはありませんか?
髪の毛や整髪料が皮膚に触れて刺激となったり、油分が付着したりするとニキビの原因になり得ます。また、ファンデーションや日焼け止めなど油分の多い化粧品の使用も、毛穴を塞ぐことで悪化の要因になります。
特にコメドジェニック(comedogenic:面皰誘発性)の成分を含むコスメは要注意です。実際に「化粧品が原因のニキビ(アクネ・コスメチカ)」は皮膚科でもよく知られており、近年の研究でも洗顔料・保湿クリーム・ファンデ等の使用がニキビリスク上昇と関連すると報告されています。
その他、長時間マスクを着けっぱなしにする生活も、マスク内の蒸れやこすれでニキビができやすくなる要因です(いわゆる「マスク荒れ」)。スポーツでヘルメットや帽子を被る機会が多いお子さんも、汗や摩擦による “機械的なニキビ”(acne mechanica)に注意が必要です。
お肌の清潔とスキンケア
「ニキビ=不潔」の誤解から、1日に何度も洗顔したり強いスクラブでゴシゴシ擦ったりしていませんか?実はそれ、逆効果の可能性があります。
不潔そのものがニキビの原因となるわけではありません。大切なのは適度な皮脂を残したやさしい洗顔です。洗いすぎは肌に必要な皮脂まで奪いバリアを壊してしまいます。
一方で洗わなすぎも毛穴詰まりのもとになるため、朝晩2回の洗顔と入浴は基本に、あとは汗をかいたときなどに軽く洗う程度で十分です。石鹸もスクラブ入りなど刺激の強いものは避け、低刺激で保湿剤配合の洗顔料を使いましょう。
ニキビ肌向けに市販されている薬用洗顔料もあります。洗顔後は油分より水分補給重視の保湿をしてあげると、皮膚の再生がスムーズになります。
スキンケアについては【Q.5】でも触れますが、「やりすぎず適度に保つ」が合言葉です。
以上のように、日頃の生活習慣を整えることはニキビ予防・改善にとても重要です。
「思春期だから仕方ない」とあきらめず、規則正しい生活・バランスのよい食事・正しいスキンケアでニキビに立ち向かいましょう。それでも重症化する場合は皮膚科での治療も検討してください。
早めに対処することでニキビは必ず良くなりますし、ニキビ跡も防げます。
お子さんのニキビに悩む親御さんも、どうか「本人の不摂生のせい」などと責めずに正しい知識でサポートしてあげてください。
※ ニキビ治療全般については「ニキビ治療専門外来」ページを参照ください。
よくある質問 FAQ
ニキビの原因についてのよくある質問をまとめました。
ご参考になれば幸いです。
顔を不潔にしているとニキビになるの?洗顔すれば防げますか?
不潔そのものが直接の原因ではありません。 実際、清潔好きで毎日しっかり洗っていてもニキビができる子はいます。
ただし皮脂や汚れを長時間放置すると毛穴づまりのもとになりますので、朝晩2回の洗顔は基本です。
ポイントは「やさしく」「落としすぎない」こと。
強い洗浄料やゴシゴシ洗いは逆効果なので避けましょう。
額の髪の毛や汗・ホコリなども刺激になるため、部活動などで汗をかいた後は軽く洗顔するか、濡れタオルで優しく拭き取ると良いです。
チョコレートやポテトチップスを食べるとニキビができるって本当?
食べ過ぎれば可能性はありますが、食品そのものが直接ニキビの原因になる科学的証拠はまだ不十分です。
かつては「脂っこい物を食べると皮脂が増えてニキビができる」と言われましたが、現在ではむしろ糖分の多い食品との関連を示す研究が増えています。
例えば清涼飲料やスナック菓子など甘い物の常習的な摂取は、ニキビ悪化と関連するとの報告があります。
一方でチョコレートや揚げ物を食べたからといって、必ずニキビが悪化するわけではありません。要はバランスの問題です。
野菜やタンパク質が不足し糖質過多の食生活にならないよう気をつけましょう。ビタミンB群やビタミンA、食物繊維などは肌の新陳代謝を助けてニキビをできにくくしてくれます。
普段の食事でこれらを意識的に摂り、甘い物・油っこい物は適量に楽しむぶんには問題ありません。
大人になったらニキビはできなくなるの?
いいえ、思春期を過ぎてもニキビができる人はいます。
特に女性は20代以降もニキビに悩むことが少なくありません。思春期のニキビと比べて、大人のニキビは生活習慣やホルモンバランスの乱れ(生理周期やストレスなど)の影響を強く受ける傾向があります。
また年齢とともにお肌の代謝が落ちるため治りづらく、慢性的に繰り返すこともあります。
ただし適切なケアと治療で改善は可能ですので、「大人ニキビだから治りにくい」などと悲観しなくても大丈夫です。思春期に比べ治療に少し時間はかかりますが、根気よく対処しましょう。
大人ニキビの陰に女性ホルモンの異常(例:多嚢胞性卵巣症候群など)が隠れている例もありますので、心配な場合は皮膚科だけでなく婦人科受診も検討してください。
ニキビはつぶしたほうが早く治りますか?
いいえ、潰すと悪化するリスクが高いです。
白い膿が見えると絞り出したくなりますが、自分で潰すと中の炎症が周囲に広がり逆に治りが遅くなります。最悪、傷跡(クレーターやシミ)が残ったり、雑菌が入って二次感染を起こすこともあります。
基本的にニキビは潰さないでください。
膿がたまったニキビは、皮膚科で専用の器具を用いて中身を排出する治療(面皰圧出)を行うことがありますが、これは無闇に潰すのとは違い、清潔な環境で適切に処置しています。
ご自宅でできるケアとしては、市販のニキビ治療薬(炎症を抑える成分配合)を塗布し清潔を保って経過を見るのが良いでしょう。どうしても気になる場合は皮膚科で相談してください。
ニキビがあるけど化粧(メイク)しても大丈夫?
メイク自体は問題ありませんが、ニキビを隠そうと厚塗りにするのはNGです。
ファンデーションやコンシーラーの厚塗りは毛穴を塞いでしまい、治りかけのニキビを悪化させる恐れがあります。また油分の多いコスメはアクネ菌のエサにもなりえます。
どうしてもメイクする場合はノンコメドジェニック(non-comedogenic)と表示されたニキビ肌対応の化粧品を選び、石鹸で優しく落とせる軽めのメイクに留めましょう。
そして帰宅後は早めにメイクオフし、毛穴に負担を残さないことが大切です。
「ニキビ肌にメイクは厳禁」ということはありませんので、校則やマナーの範囲内で上手に付き合ってくださいね。
メイクをする分、普段以上にクレンジングと保湿ケアを丁寧に行うようにしましょう。
寝不足だとニキビが増えますか?
はい、睡眠不足はニキビを悪化させる大きな要因です。
睡眠中には皮膚の修復やホルモンの調整が行われています。特に夜10時〜2時頃は「お肌のゴールデンタイム」とも呼ばれ、成長ホルモンが分泌されて肌細胞のダメージ修復が盛んになります。
寝不足や夜更かしでこの時間帯の睡眠が不十分だと、肌の生まれ変わりが滞り、毛穴の詰まりを促進したり炎症を沈める力が弱まったりします。
また寝不足そのものが体にストレスと似た状態を引き起こし、男性ホルモンやストレスホルモンの分泌を増やすこともわかっています。そのため徹夜や連日の睡眠不足でニキビが急に増えた…というケースは珍しくありません。
逆に言えば、十分な睡眠をとるとニキビが改善する可能性があります。事実、ニキビ患者さんを対象にした調査で、睡眠の質を高めたところ症状が和らいだという報告もあります。
結論: 「お肌のために睡眠は欠かせない」は本当です。
最低でも6時間、できれば毎日7〜8時間の睡眠を目標にしてみてください。それが難しい場合も、週末にしっかり休むなど睡眠負債を解消する習慣を持つと良いでしょう。
思春期ニキビと大人ニキビの原因はどう違いますか?
思春期ニキビはホルモン急増による皮脂過剰が主因で、額や鼻など皮脂分泌の盛んな部位にできやすいのが特徴です。
一方、大人ニキビはホルモンの周期的な乱れに加え、ストレスや生活習慣、化粧品の影響など複合的要因で起こります。特に20代以降の女性は生理前後のホルモンバランス変化や日々のストレスであご周りにニキビが出やすくなります。
ただし両者とも基本的な発生メカニズム(毛穴詰まり→菌増殖→炎症)は同じなので、原因の違いに合わせたケアが大切です。思春期は皮脂コントロール中心、大人ニキビは生活習慣改善や必要に応じホルモン治療を検討します。
ストレスを感じるとなぜニキビが増えるのでしょうか?
ストレス時には体内でストレスホルモン(コルチゾール等)が分泌され、これが皮脂腺を刺激したり免疫バランスを崩して毛包周囲の炎症を悪化させるためと考えられます。
またストレスが溜まると生活リズムも乱れ、睡眠不足や食生活の偏りが生じてニキビ悪化の悪循環になります。
さらに最近の知見では、ストレスにより肌の防御機能が低下しアクネ菌への反応性が高まる可能性も示唆されています。
要は心と肌はつながっているということです。
対策として、適度にリラックスする時間を持ち十分な睡眠をとること、運動や趣味でストレスを発散することがニキビ予防につながります。
生理前になると毎回あごや口周りにニキビができます。これはホルモンのせいでしょうか?
はい、ホルモンの影響が大きいと考えられます。
女性の生理周期では、排卵後〜月経前にかけて黄体ホルモン(プロゲステロン)が増えます。プロゲステロンには皮脂分泌を促進する作用や、皮膚をややむくませて毛穴を狭くする作用があるため、この時期に毛穴が詰まりやすく皮脂も増えることでニキビができやすくなります。
特にあごやフェイスラインは大人ニキビが出やすい部位で、生理前に同じ場所に繰り返す方も多いです。
また生理前は自律神経が乱れ気味になりストレス耐性が落ちたり、甘いものを食べたくなったりすることもニキビ悪化につながると言われます。
生理前のニキビは月経前症状(PMS)の一つとも言え、女性ならではのホルモン変化による現象です。対策としては、低用量ピルの服用でホルモンバランスを安定させたらニキビが出にくくなるケースがありますので、産婦人科や皮膚科で相談してみるのも一つの手です。
また生理前〜生理中は睡眠と栄養をいつも以上にしっかりとり、肌を清潔かつ保湿重視で優しくケアするよう心がけましょう。
親もニキビに悩んでいました。ニキビは遺伝しますか?
ニキビそのものが親から子へ遺伝するわけではありませんが、「ニキビの出来やすさ」はある程度遺伝的な体質,遺伝的な要因に影響されます。
(※遺伝と聞くと失望される方もいらっしゃるので先にお伝えしますが、遺伝的ニキビ発症リスクが最も高いグループでも、普通の人より発症率はせいぜい1.6倍程度と報告されています。後述します。)
親や兄弟姉妹にニキビの経験がある場合、子どももニキビができやすい傾向があります。ただし「遺伝する」と言っても必ず発症するわけではなく、環境や生活習慣の影響も受けます。以下に、遺伝とニキビの関係について分かりやすく説明します。
ニキビと遺伝の関係:研究からわかること
ニキビは思春期から若い年代で非常に一般的な皮膚トラブルで、多くの患者さんで家族に同じ悩みを持つ人がいることがわかっています。
実際、ニキビ患者さんの多くは親や兄弟姉妹にもニキビの既往歴があると報告されています。たとえばイギリスの研究では、25歳を過ぎてもニキビが続く患者のご家族(第一度近親者)では17%にニキビが見られましたが、ニキビのない方のご家族では5%に留まりました。統計的に見ると親族にニキビ患者がいるといない場合に比べて約4倍もニキビになりやすいとの結果です。
また、双子の研究からもニキビのなりやすさに強い遺伝的影響があることが示されています。たとえば400組以上の女性双生児を対象にした大規模研究では、ニキビ体質であることの約81%が遺伝要因によって説明できると推定されました(残り19%は本人固有の環境要因による)。別の双子研究(オーストラリアの10~24歳の双子約4,500人規模)でも、ニキビの重症度の遺伝率は約85%と非常に高い数値が報告されています。このように「ニキビになりやすいかどうか」は大部分が遺伝で決まることが現在の研究で明らかになっています。
さらに家族歴がある場合、ニキビの出始める時期が早まることも知られています。家族にニキビ経験者がいる10代の患者は、そうでない人に比べて思春期前からニキビが出る割合が高いとの報告があります。実際、親にニキビがあった人では子どもも思春期前からニキビが始まるケースが多いのです。
また同じ報告では、家族歴のある患者は治療後に再発しやすい(若い頃に重症化しやすく、抗生剤やイソトレチノイン治療後にニキビが戻りやすい)傾向も指摘されています。これらは遺伝的な肌質がニキビの経過にも影響を与えうることを示唆しています。
とはいえ、遺伝ですべてが決まるわけではありません。 仮に親御さんが若い頃に重症のニキビで悩んでいたとしても、お子さんが必ずしも同じ程度のニキビに悩むとは限りません。たとえば、最新の大規模研究によれば、現在までに見つかっているニキビ関連の遺伝子変異をすべて考慮してもニキビ発症リスクの約10%しか説明できないとされています。また、遺伝的なリスクが最も高い上位5%の人でも、平均的なリスクの人に比べて発症率はせいぜい1.6倍程度と報告されています。
言い換えれば、どんなに遺伝的素因が強くても、環境要因や適切なケアによって十分に対策可能なのです。
遺伝で受け継がれる「ニキビ体質」とは
では、遺伝的に受け継がれる「ニキビができやすい体質」とは具体的に何でしょうか。ポイントとなるのは以下のような要素です:
皮脂の分泌傾向(脂性肌かどうか)
肌の脂(皮脂)を出す皮脂腺の働きには個人差があり、これは遺伝の影響を強く受けます。家族に脂性肌の方が多い場合、お子さんも皮脂腺が活発で毛穴が詰まりやすい傾向を引き継ぐことがあります。実際、一卵性双生児(遺伝子が全く同じ)のペアでは皮脂の分泌量や成分組成まで非常によく似ることが報告されています。皮脂が多いと毛穴に皮脂と古い角質が詰まりやすく、ニキビの初期段階である「コメド(面ぽう)」ができやすくなります。
ホルモンに対する応答性
思春期に体内で増えるアンドロゲン(男性ホルモン)は皮脂の分泌を促し、ニキビの大きな誘因となります。遺伝的にホルモンの影響を受けやすい肌質の方は、この思春期の変化で一気にニキビが出やすくなります。
例えば男性ホルモンの感受性や分泌量を左右する遺伝子に変異があると、皮脂腺が過剰に刺激されてニキビ体質になり得ます。実際の研究でも、ホルモン調節に関わる特定の遺伝子変異(MYC遺伝子という細胞増殖やホルモン応答に関連する遺伝子の近くにある変異)を持つ思春期の若者は、ニキビが重症化しやすいことが報告されています。
肌の炎症反応の起こりやすさ(炎症への感受性)
ニキビでは毛穴に常在する皮膚の細菌(アクネ菌、現在の名称ではCutibacterium acnes)に対する免疫反応が重要です。免疫の働き方にも個人差があり、これも遺伝要因に左右されます。炎症を促すサイトカイン(免疫物質)の遺伝子には多様なタイプがあり、一部のバリエーションはニキビの重症度に関連することが分かっています。
例えばTNF-α(腫瘍壊死因子)やインターロイキン(IL-1など)といった炎症性サイトカインの遺伝子多型によって、炎症の強さや持続時間が変わります。
ある研究では、炎症に関与する遺伝子(TNFやIL群)や皮脂腺の機能に関与する遺伝子(CYP17A1[ステロイド代謝酵素]やFST[毛包の増殖調節因子]など)の変異がニキビの発症・悪化リスクに影響すると結論づけられています。
つまり、生まれつき炎症を起こしやすい肌質の人は、同じ毛穴詰まりでも強い赤み・腫れが出てニキビが悪化しやすいのです。
毛穴の構造や肌質
毛穴(毛包)周囲の角質細胞の性質や、皮膚のターンオーバー(生まれ変わり)の速さにも遺伝的な違いがあります。遺伝により角質が厚くなりやすい、毛穴が狭い、詰まりを押し出す力が弱いといった肌質は、ニキビの「芯」ができやすくなります。また、近年の遺伝学研究からは毛包や皮脂腺の形成・維持に関わる遺伝子にもニキビとの関連が見つかっています。例えばWntシグナルという毛穴の幹細胞を制御する経路や、皮脂中の脂質を作る酵素(FASNやFADS2など)の遺伝子に変異があると、毛包環境がニキビに傾きやすい可能性があります。
以上のように、「ニキビができやすい体質」には様々な側面があり、それぞれに対応する遺伝的素因が考えられます。ご家族にニキビ体質の方がいる場合、お子さんも「皮脂が多く毛穴が詰まりやすい」「ホルモンの影響を受けやすい」「炎症反応が強く出る」などの傾向をいくつか受け継いでいるかもしれません。
ただ、その傾向があっても実際にニキビが悪化するかどうかは生活環境やケアによって大きく左右します。
遺伝的素因があっても大丈夫:対策と安心ポイント
親御さんとして「自分がニキビ肌だったから、子も同じ苦労をするのでは」と心配になるかもしれません。しかし、遺伝的な体質があっても適切な対策でニキビは十分コントロール可能です。
思春期のニキビは非常に一般的で、全体の約85%の若者が多少なりとも経験するものです。まずは「うちの子だけが特別にひどくなるのでは」と過度に不安にならず、規則正しい生活や正しいスキンケア習慣を身につけることが大切です。
具体的には、毛穴を清潔に保つ洗顔習慣、脂質や糖分を摂りすぎないバランスの良い食事、十分な睡眠とストレス管理などがニキビ予防に役立ちます。遺伝的に皮脂が多めの肌質でも、適度な洗顔と保湿で毛穴詰まりを減らすことができますし、炎症が起きやすい方でも早めに皮膚科で治療(抗炎症の塗り薬など)を始めれば悪化を防げます。
医師の視点から言えば、家族にニキビ体質があっても過度に心配しすぎる必要はありません。 むしろ「うちの子は少しニキビができやすいかも」と傾向を把握しておくことで、早め早めのケアや受診につなげることができます。
ニキビは適切な治療で改善しますし、今では良いお薬やケア用品がたくさんあります。ご家族で共有された体質について前向きに捉え、必要に応じて専門医に相談しながら、お子さんの肌を見守っていきましょう。
ニキビの原因菌はアクネ菌だと聞きますが、殺菌すれば治りますか?
アクネ菌(正式名: Cutibacterium acnes)はニキビの炎症を引き起こす直接的な菌です。
しかし、アクネ菌だけが原因ではないことに注意が必要です。
毛穴の詰まりや皮脂の蓄積といった「土台」があるからこそアクネ菌が増殖してニキビになります。したがって、殺菌すればニキビが即治るわけではありません。
実際、抗生物質の塗り薬や飲み薬でアクネ菌を減らす治療を行うと一定の効果はありますが、それだけでは不十分で、再発も多いです。
近年は抗生物質の長期使用による耐性菌の問題もあり、むやみに「殺菌頼み」にしない方針が主流です。皮膚の常在菌バランスも大切ですから、善玉菌まで殺しすぎないようにしなければなりません。
アクネ菌対策(殺菌)はニキビ治療の一部として有効ですが、「毛穴づまりの解消」「皮脂分泌の抑制」とセットで考える必要があります。皮膚科では抗菌薬も必要時使用しますが、ピーリングやホルモン治療なども組み合わせ、総合的にニキビの原因にアプローチします。
大人ニキビが繰り返しできて治りません。生活も気を付けて薬も塗っているのに、何が原因なのでしょう?
大人ニキビが長引く場合、一つの原因ではなく複数の要因が絡んでいることが多いです。
例えば、ストレスや睡眠不足でホルモンバランスが乱れ皮脂が増えているところに、合わない化粧品で毛穴が詰まり、さらに乾燥でバリアが壊れて炎症が悪化…といった具合に、原因の重なりが起きているかもしれません。
市販薬や塗り薬で改善しない場合、塗り薬では届かない体内のホルモン調整や毛穴の特殊なケアが必要なケースもあります。
また、ニキビのタイプによって有効な治療は異なります。いわゆる白ニキビ・黒ニキビばかりならピーリングやスキンケアの見直しが有効ですが、赤く腫れる炎症性ニキビが多いなら抗炎症剤や抗生剤の服用が必要かもしれません。
さらに、実はニキビではなく別の疾患(マラセチア毛包炎や皮膚の別の病気)という可能性もゼロではありません。
いろいろ試しても治らないニキビは、自己判断だけでは原因を見分けるのが難しいです。
皮膚科クリニックで相談し、必要に応じた各種検査等を行ない、根本原因に合わせた治療を検討することをおすすめします。
当院のニキビ治療専門外来でも「何をしても治らなかった」方が多く受診されますが、一人ひとりの原因を丁寧に探り、総合的な治療で改善を促していきます。
メイクや日焼け止めでニキビが悪化することはありますか?
はい、使用する化粧品によってはニキビが悪化する場合があります。
特に油分の多いファンデーションや日焼け止め・クリームなどは、毛穴を物理的に塞いでしまったり、油分が酸化して刺激になったりすることがあります。
また、一部の化粧品成分(ラノリン、赤色顔料、オクチルステアレートなど)はコメド(毛穴の角栓)の形成を促しやすいことが知られており、これらを含む製品を使うとニキビができやすい肌質の人では悪影響を受ける可能性があります。
最近はノンコメドジェニックを謳う製品も増え、安全性は高まっていますが、それでも100%ニキビができない保証はありません。
使用後は丁寧にクレンジングして肌に残さないようにしましょう。ただし、過度のクレンジングや洗顔、スクラブ洗顔やピーリングのやりすぎも要注意です。
一時的に角質を取っても刺激でかえって皮膚が厚くなったり乾燥して悪循環になることがあります。基本は優しい洗顔(1日2回まで)と十分な保湿です。
ニキビ肌でも保湿は必要なので、ヒアルロン酸やセラミド配合の低刺激保湿剤でしっかり潤いを与えてください。
それでも不安な場合、皮膚科で相談すれば肌質に合ったメイク用品のアドバイスも受けられます。
ビタミンC配合の美容液を使ったらニキビが悪化した気がします。ビタミンCはニキビに良いと聞きますが、なぜでしょうか?
ビタミンC(アスコルビン酸)はニキビ跡の色素沈着改善や皮脂抑制効果が期待できる有用な成分です。そのため多くのニキビ肌向け化粧品に配合されています。
ただ、高濃度のビタミンC美容液は人によっては刺激が強く感じられる場合があります。
ビタミンC誘導体美容液の種類によっては、酸性度が高いため肌が敏感な方だと塗布後にピリピリしたり赤みが出たりすることがあります。こうした刺激によって一時的に炎症が悪化し、ニキビが増えたように感じた可能性があります。
また美容液の基材(例えばオイルや他の添加物)が肌に合わなかったケースも考えられます。
ビタミンCそのものはニキビに良い成分ですが、製品の処方や濃度によっては肌に合わないこともあるということです。
使用してヒリヒリするようなら無理に続けず、一旦中止しましょう。
より低濃度のものや他の有効成分(例えばナイアシンアミドやバクチオール配合の美容液など)、あるいは皮膚科処方の外用薬(ビタミンCローションなど)に切り替える方法もあります。
スキンケアで迷ったときは医師や薬剤師に相談し、自分の肌に合うものを見つけてください。
監修者情報(医師紹介)
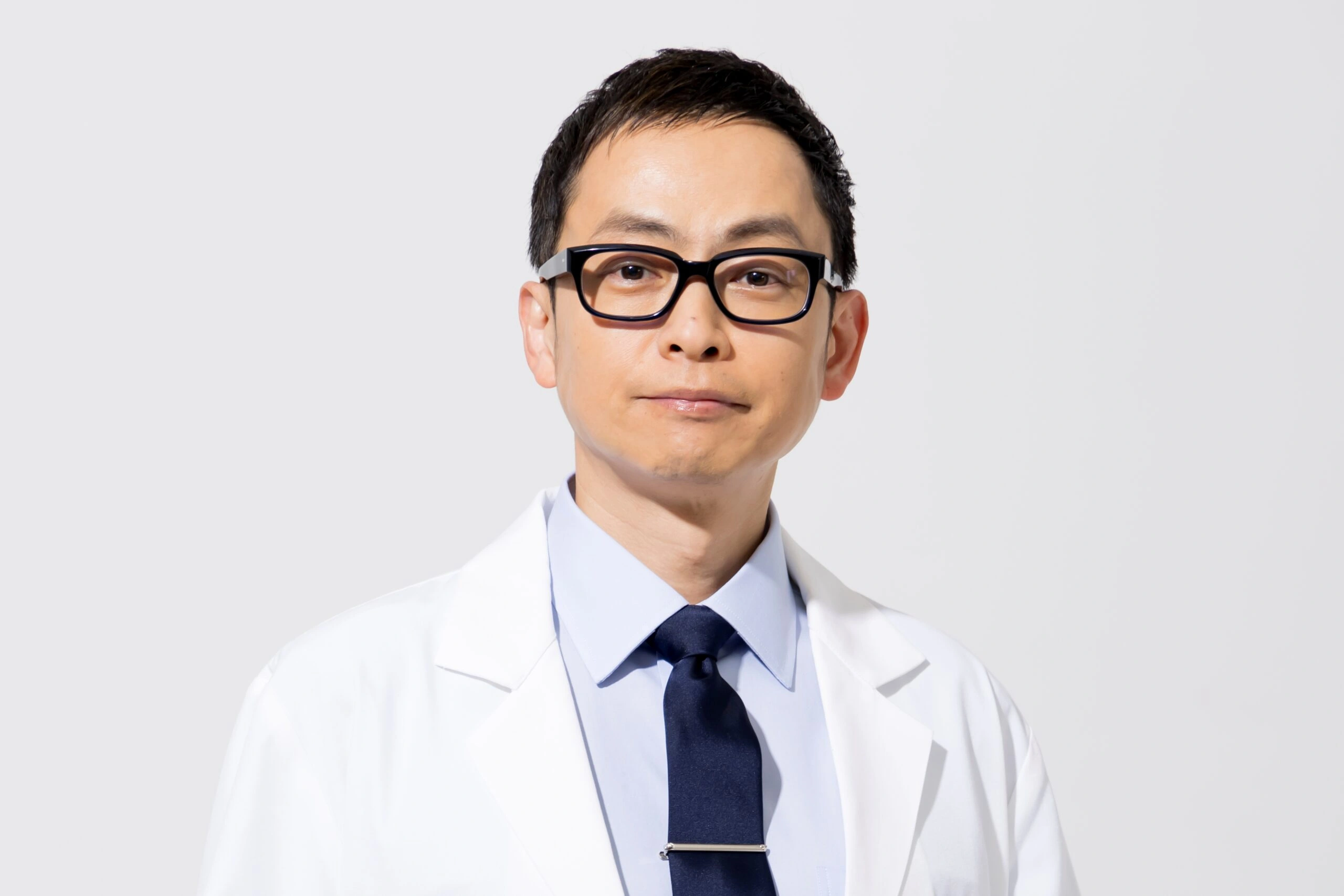
監修医師:佐藤 雅樹 (さとう まさき)
ソララクリニック 院長
専門分野:美容皮膚科
2000年 順天堂大学医学部卒。順天堂大学医学部形成外科入局。 大学医学部付属病院等を経て、都内美容皮膚科クリニックにてレーザー治療の研鑽を積む。2011年3月 ソララクリニック開院 院長就任。2022年 医療法人 松柴会 理事長就任。日本美容皮膚科学会 日本形成外科学会 日本抗加齢医学会 日本レーザー医学会 点滴療法研究会 日本医療毛髪再生研究会他所属。
様々な医療レーザー機器に精通し、2011年ルビーフラクショナル搭載機器を日本初導入。各種エネルギーベースの医療機器を併用する複合治療に積極的に取り組む.
最終更新日
参考文献
本ページを作成するに当たり参考にした論文を紹介します。
それぞれ要約していますので、参考にしてみてください。
ニキビ(尋常性ざ瘡):病態生理、治療および最近のナノテクノロジーの進歩に関するレビュー
原題: Acne vulgaris: A review of the pathophysiology, treatment, and recent nanotechnology based advances
出典: Biochemistry and Biophysics Reports
DOI: 10.1016/j.bbrep.2023.101578
要約: 世界的にニキビは思春期の85%以上で発症し、皮脂の過剰・毛包の角質異常・アクネ菌増殖・炎症の4つが病因の主要因であることが解説されています。近年の治療法や新技術(ナノテクノロジー応用)についても最新知見を網羅した総説。
尋常性ざ瘡(ニキビ)
原題: Acne vulgaris
出典: Nature Reviews Disease Primers
DOI: 10.1038/nrdp.2015.29
要約: ニキビは毛包を中心とした慢性炎症疾患であり「成長過程だから仕方ない」というものではないこと、発症には皮脂腺の機能異常(皮脂の過剰・脂質組成の変化)やホルモン環境の乱れ、毛包の過角化、炎症と免疫反応など複数の要因が複雑に絡むことが示されています。効果的な予防・治療にはこうした病態生理の初期過程を狙ったアプローチが重要と提言されています。
皮脂腺の恒常性とニキビ病態形成のメカニズム
原題: Homeostasis of the sebaceous gland and mechanisms of acne pathogenesis
出典: British Journal of Dermatology
DOI: 10.1111/bjd.17981
要約: 皮脂腺の構造と機能、そしてニキビができるメカニズムについて詳しく論じたレビュー論文です。
皮脂分泌の調節機構(ホルモンや遊離脂肪酸・神経ペプチドの関与)や、アクネ菌が形成するバイオフィルムと炎症反応との関係など、ニキビ発症の生物学的プロセスが解説されています。
これらの知見は新たな治療標的の研究にもつながっています。
ニキビの疫学に関する系統的レビュー
原題: Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris
出典: Scientific Reports
DOI: 10.1038/s41598-020-62715-3
要約: 全世界の多数の研究データを分析。ニキビは世界人口の約9.4%に影響を与え、皮膚疾患の中で8番目に多く罹患する疾患であることを示した論文。
地域差では西欧や中東で有症率が高い傾向が報告され、思春期中心ではあるが成人まで持続する例も少なくないとされています。ニキビが患者の生活の質に与える影響(心理社会的負担)や、重症度評価法の課題についても言及されています。
尋常性ざ瘡の治療ガイドライン
原題: Guidelines of care for the management of acne vulgaris
出典: Journal of the American Academy of Dermatology
DOI: 10.1016/j.jaad.2015.12.037
要約: 米国皮膚科学会によるニキビ治療のガイドライン(2016年)。
毛穴の閉塞・皮脂過剰・アクネ菌増殖・炎症という4大要因に対応した治療戦略が推奨されており、治療選択は病型や重症度に応じて組み合わせることが推奨されています。
近年注目の食事(高GI食品・乳製品)や生活習慣(ストレス・喫煙・睡眠)については、エビデンスが限定的ながらも ニキビ悪化因子となりうる と言及されています。
患者への指導では生活面のバランスを整えるよう助言すべきとしています。
成人女性におけるニキビの病因:系統的レビュー
原題: Etiology of Adult Female Acne – Systematic Review
出典: Health Science Reports
DOI: 10.1002/hsr2.70697
要約: 25歳以上の女性に見られる「大人ニキビ」の原因について最新知見をまとめたレビュー(2025年)。
特に、男性ホルモン(高アンドロゲン血症)が皮脂腺を刺激しニキビの一因となること、家族歴(遺伝要因)を持つ人は成人後もニキビが出やすいこと、そして高糖質な食生活が皮脂分泌を増やすインスリン様成長因子IGF-1の上昇を介してニキビを悪化させうることが強調されています。
以上の点から、成人女性のニキビではホルモン治療や栄養指導を含めた包括的対策の重要性が示唆されています。
食事とニキビ:系統的レビュー
原題: Diet and acne: A systematic review
出典: JAAD International
DOI: 10.1016/j.jdin.2022.02.012
要約: 食生活がニキビに与える影響について高品質な研究を網羅的に評価した論文。
高GI(グリセミック指数)食品の過剰摂取はニキビの発生・悪化と有意な関連があること、一方で乳製品の影響については人口集団や性別によって結果がまちまちで明確な結論には至っていないことが報告されました。
総じて、「高血糖指数の炭水化物や糖分の多い食事は控えめが無難だが、完全除去よりバランスが大事」「牛乳については人によるのでニキビと明らかに関連するようなら摂取量を見直す」といった提言がなされています。
成人のニキビと食習慣の関連:NutriNet-Santéコホート研究
原題: Association Between Adult Acne and Dietary Behaviors: Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study
出典: JAMA Dermatology
DOI: 10.1001/jamadermatol.2020.1602
要約: フランスの大規模ウェブ調査に基づく研究で、現在ニキビに悩む成人は、悩んでいない人に比べて「牛乳」「清涼飲料」「お菓子など高脂肪・高糖質食品」の摂取頻度が有意に高かったと報告されました。
これらの食品群の摂取量が多い人ほど 現在進行形のニキビを有する割合が高い 傾向が示されており、食事とニキビ悪化の関連を裏付けるエビデンスとして注目されます。
ただし観察研究のため因果関係の断定はできず、「甘い物・乳製品の控えめな摂取」が推奨される一方で更なる検証研究が求められています。
ストレスとニキビの関連(サウジアラビア女子医学生を対象とした研究)
原題: The association between stress and acne among female medical students in Jeddah, Saudi Arabia
出典: Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
DOI: 10.2147/CCID.S148499
要約: 144名の女子医学生を対象にストレス度とニキビ重症度の関係を調べた研究。結果、ストレスレベルが高い学生ほどニキビ病変数・重症度が有意に高かったことが示されました(p<0.01)。このことから、心理的ストレスがニキビの悪化要因になりうることが支持されています。
著者らはリラクゼーションやストレスマネジメントがニキビ改善に有用である可能性にも言及しており、心身のケアの重要性を示唆する内容です。
化粧品使用とニキビリスク:症例対照研究
原題: A Case-Control Study Exploring the Association Between Cosmetic Use and Acne Risk: Implications for Prevention and Clinical Practice
出典: Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
DOI: 10.2147/CCID.S533950
要約: 2022~2023年に中国で行われた症例対照研究(対象:化粧習慣のある女性151名)で、洗顔料・保湿剤・ファンデーション・フェイスパウダーの使用がニキビ発症リスクの有意な上昇と関連したことが報告されました。
特に「面皰形成(コメドジェニック)」作用のある成分を含むクレンジングや保湿剤の使用でニキビリスクが約2.5倍に増加しており、化粧品中の成分による毛穴つまりの影響が示唆されています。
本研究は Acne cosmetica(化粧品誘発性ニキビ)のリスクを定量的に示したものであり、ニキビ予防にはノンコメドジェニック化粧品の選択や正しいスキンケアが重要であることを裏付けています。
ニキビに関連する新たな遺伝要因の発見(ゲノムワイドメタ解析)
原題: Genome-wide meta-analysis identifies novel loci conferring risk of acne vulgaris
出典: European Journal of Human Genetics
DOI: 10.1038/s41431-023-01326-8
要約: 多民族約20万人規模のゲノム解析データを統合し、ニキビの発症素因に関与する17の新規遺伝子座を同定した研究(2023年)。
これらの遺伝的変異は毛包の構造や免疫応答、ホルモン代謝に関わる遺伝子上に存在し、ニキビの体質に遺伝要因が寄与することを強く示しています。
将来的に、こうした遺伝情報に基づく個別化医療(ニキビのリスク予測やオーダーメイド治療)への発展も期待される成果です。
皮膚常在菌叢の乱れとアクネ菌バイオフィルム(思春期ニキビ病変部の検討)
原題: Skin dysbiosis and Cutibacterium acnes biofilm in inflammatory acne lesions of adolescents
出典: Scientific Reports
DOI: 10.1038/s41598-022-25436-3
要約: 思春期の重症ニキビ患者の皮膚を調べ、ニキビ部位では健康な肌と比べて常在菌の多様性低下(菌叢バランスの乱れ)が起きていること、またアクネ菌がバイオフィルムを形成して皮膚に定着・集団化している証拠が見出されました。
バイオフィルムとは菌が作る粘膜状の膜で、抗菌薬や免疫から菌を守るためニキビの治りにくさの一因と考えられます。
本研究は、皮膚の微生物バランスを整える(肌の善玉菌を維持する)ケアやバイオフィルム対策がニキビ治療に有効かもしれないことを示唆しています。
低GI負荷の食事によるニキビ症状改善:RCT
原題: A low-glycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial
出典: American Journal of Clinical Nutrition
DOI: 10.1093/ajcn/86.1.107
要約: ニキビに悩む男性を低グリセミック負荷食(低GI・高タンパク質)群と従来食群に分け12週間追跡したランダム化試験です。
結果、低GI食群ではニキビの吹き出物の数(皮疹数)が有意に減少し、インスリン代謝の指標も改善しました。一方、対照の高GI食中心群では減少が少なく、体重やインスリン抵抗性の悪化もみられました。
この研究は食事の血糖負荷を下げることでニキビが改善しうることを示した初めてのRCTであり、「食生活の見直しはニキビ対策として有効かもしれない」というエビデンスとして引用されています。
ニキビの発症における遺伝と環境要因の影響:女性のニキビに関する双子研究
原題: The influence of genetics and environmental factors in the pathogenesis of acne: a twin study of acne in women
出典: Journal of Investigative Dermatology
DOI: 10.1046/j.1523-1747.2002.19621.x
要約: 458組の女性双子を対象にニキビ体質への遺伝寄与を解析した研究。
ニキビの発症率の約81%が遺伝要因によると推定され、残り19%が環境要因とされた。
遺伝の影響が非常に強いことが示され、ニキビの原因遺伝子を探る重要性が示唆された
遺伝はニキビの予後に影響するか(遺伝:ニキビの予後因子)
原題: Heredity: a prognostic factor for acne
出典: Dermatology(Karger)
DOI: 10.1159/000090655
要約: ニキビ患者151名について家族歴の有無で比較した前向き研究。
家族歴がある群はニキビの発症が早く(思春期前から出現しやすい)、治療に経口薬を要する例や治療後に再発する例が多かった。特に母親由来の家族歴があると面ぽう(毛穴のつまり)病変が多く見られた。
遺伝的素因のあるニキビは若年期に重症化しやすく治療抵抗性になりうることを示している
尋常性ざ瘡(ニキビ)
原題: Acne vulgaris
出典: The Lancet
DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60321-8
要約: ニキビの病態と治療についてまとめた総説。ニキビの原因は多因子(皮脂の増加、毛包の角化異常、アクネ菌増殖、炎症など)であり、遺伝要因も重要な役割を果たすと解説されている。
家族歴・双子研究からニキビの遺伝率がおよそ80%と非常に高いことが紹介され、遺伝と環境の両面からニキビ発症メカニズムを論じている。
ゲノム解析で重症ニキビの新規感受性遺伝子座を3か所同定
原題: Genome-wide association study identifies three novel susceptibility loci for severe acne vulgaris
出典: Nature Communications
DOI: 10.1038/ncomms5020
要約: 重症ニキビ患者約1,893名と対照5,132名(英国)を対象にゲノムワイド関連解析を行い、ニキビ感受性に関連する3つの新しい遺伝子領域(11q13.1、5q11.2、1q41)を発見した研究。
これらの領域にはTGF-βシグナル経路に関与する遺伝子(例:OVOL1, FST, TGFB2)が含まれ、ニキビ患者の皮膚ではそれらの遺伝子の発現が低下していた。
皮膚の炎症調節に関わるTGF-β経路の乱れがニキビの発症に寄与する可能性が示された。
重症ニキビに関連する新規感受性遺伝子座1q24.2および11p11.2の発見
原題: Two new susceptibility loci 1q24.2 and 11p11.2 confer risk to severe acne
出典: Nature Communications
DOI: 10.1038/ncomms3870
要約: 中国人(漢民族)1,056名ずつの患者群と対照群を用いた初のニキビGWAS研究。結果として1q24.2と11p11.2の2か所の遺伝子座が重症ニキビに有意に関連していることが判明した。
各変異の効果量(オッズ比)は約1.2倍程度と小さいものの、ニキビの遺伝率が高いことから他の遺伝要因の存在が示唆され、より大規模な研究の必要性が述べられた。
欧州系米国人における重症思春期ニキビのゲノムワイド関連解析
原題: A genome-wide association study of severe teenage acne in European Americans
出典: Human Genetics
DOI: 10.1007/s00439-013-1374-4
要約: 欧州系アメリカ人を対象に思春期ニキビの遺伝因子を探索した研究。
81名の重症ニキビ患者と847名の対照でGWASを行い、8q24領域の遺伝子変異(rs4133274、MYC遺伝子近傍)が重症ニキビと最も強く関連することを発見した。
この変異を持つとニキビ発症リスクがおよそ4倍に増加し、ホルモン調節に関与するMYC遺伝子周辺の異常が思春期ニキビの一因となりうることが示唆された。
オーストラリアの思春期双生児におけるニキビの遺伝率とGWAS解析
原題: Heritability and GWAS Analyses of Acne in Australian Adolescent Twins
出典: Twin Research and Human Genetics
DOI: 10.1017/thg.2017.58
要約: 10~24歳の双生児4,491名(+兄弟姉妹271名)を対象にニキビ重症度の遺伝的影響を評価した研究。一卵性双生児ではニキビ重症度の一致度が高く、遺伝要因の寄与率は約85%と推定された。
また同時にGWASも行われ、皮脂腺の分化制御に関与するPIK3R1遺伝子近傍など3つの領域にニキビ重症度との関連シグナルが検出された(統計的有意水準には達しないものの有望な候補)。
ニキビの発症に強い遺伝要因がある一方、明確な原因遺伝子の特定にはさらなる研究が必要とされた。
全ゲノムメタ解析でニキビの新規リスク遺伝子座を複数発見
原題: Genome-wide meta-analysis identifies novel loci conferring risk of acne vulgaris
出典: European Journal of Human Genetics
DOI: 10.1038/s41431-023-01326-8
要約: ニキビ患者34,422人・対照364,991人という大規模データのメタ解析研究。
既知の19遺伝子座を再確認し、新たに4つの感受性遺伝子座(例:脂質代謝酵素FADS2やFASN、毛包関連因子LGR5、Wnt経路調節因子ZNRF3/KREMEN1)を同定し、報告済みのニキビ関連遺伝子座は計50箇所となった。
しかしこれら遺伝子変異で説明できるニキビのリスクは全体の約9.4%に過ぎないことも示され、ニキビの遺伝的素因は、多数の遺伝子のわずかな積み重ねであることが示唆された(遺伝リスク上位5%の人でも発症率は平均の1.6倍程度)。
成人期ニキビの家族リスク:患者と非患者の近親者比較
原題: The familial risk of adult acne: a comparison between first-degree relatives of affected and unaffected individuals
出典: British Journal of Dermatology
DOI: 10.1046/j.1365-2133.1999.02979.x
要約: 思春期以降もニキビが持続する成人患者204名と非ニキビ対照者144名について、それぞれの第一度近親者(親・兄弟姉妹・子)のニキビ有病率を調べた研究。
患者群の近親者1,203名中203名(17%)にニキビが認められたのに対し、対照近親者856名中では42名(5%)のみだった。
家族に患者がいるといない場合に比べ約4倍ニキビになりやすい計算となり(OR=3.93)、遺伝的要因が個人のニキビ感受性に重要であることを裏付けた。
尋常性座瘡に関連する遺伝子変異(総説)
原題: Genetic Variants Associated with Acne Vulgaris
出典: International Journal of General Medicine
DOI: 10.2147/IJGM.S421835
要約: 近年報告されたニキビ関連遺伝子を網羅的にまとめたレビュー論文。
免疫の働きに関与するサイトカイン(インターロイキンIL群、TNFなど)や、皮脂分泌や角質代謝に関与する酵素(CYP450ファミリー、レチニンRETN、MMP/TIMPなど)の遺伝子多型がニキビの発症や重症化に影響しうると解説されている。
特に炎症反応を左右する遺伝子変異や皮脂腺の活動性を決める遺伝子変異はニキビの進行度や瘢痕の残りやすさにも関与する可能性があり、ハイリスク者の早期介入による瘢痕予防の重要性が述べられている。